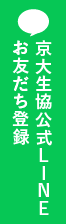合格体験記
合格体験記

 合格体験記
合格体験記
このページはただいま準備中です。
2025年の情報をご覧いただけます。
2025年度の情報をご覧いただけます
2025年度合格者の体験記
総合人間学部
総合人間学部:文系
ペンネーム:みんとぐりーん
●京大を目指したきっかけ
中学生のころから「人間って何だろう」「人間の心ってどういう動きをしているのだろう」ということに興味があったものの、臨床心理学や哲学の本を読んでは「なんかちがうなあ」と思っていました。心理学をやりたいという漠然とした思いはありつつも一般的な心理学専攻への不和感を抱いていた中、総合人間学部に出会い、自分が気になっていることが学べる環境だと考えて志望しました。
関東の進学校である出身高校の中で、多くの人が東大を志望する流れに逆らいたいという思いもあり、京大総合人間学部は私の考えにぴったりでした。
●受験勉強の仕方
私はモットーとして「全科目満点取れば合格するに決まっている」を掲げて勉強していました。実際のところ京大の国数英は全記述なので、満点を取るのは限りなく難しいですが、その上で自分ができるベストを常に尽くそうと思っていました。精神論に聞こえるかもしれませんが、初めから諦めているのではそれ以上の成長はできません。モチベーションを保つためには高い目標が必要だと思います。
国語と数学は結局理解力とひらめき力に収束すると思っていたので、問題を解いて復習するサイクルで問題数をこなして力を鍛えました。
英語に関しては、ずっと単語力が不足していると感じていたので、単語帳を回したり読んだ文章で見かけた単語を自作単語帳にまとめたりしていました。単語帳サイズの冊子を使うのが好きではなかったので、スマホのアプリを活用しました。
社会(日本史)は、傾向的に基本的な知識を増やしていくのが有効だと考えていたので、教科書を読みこみました。問題などで見かけた単語を教科書上でマークしていき、教科書に色がつく快感を楽しんでいました。 受験勉強をするうえで、問題との相性はかなり大事にしていました。私は京大の入試形式、そして問題の雰囲気が大好きなので、楽しく勉強できていました。一方で私立対策は正直かなり苦痛だったのでほとんどやりませんでした。その結果抑えのつもりで出願した私立の一般入試で不合格だったので、私立もきちんと取りたい人は多少我慢して対策をすることをお勧めします。
●受験生に向けて一言
受験は一人でするものではありません。自分のベストを尽くしたうえで、採点者(大学の先生)がどう判断するかによって結果が変わります。また、周りの人が支えてくださるからこそ勉強できて、受験できることも忘れてはいけません。感謝を忘れず、みなさんのベストを尽くしてください。応援しています!
総合人間学部:理系
ペンネーム:はくまい
●京大を目指したきっかけ
高校一年生のとき、将来やりたいことが明確に定まっていないなか、どこの学部学科を目指そうかなと考えている際に出会ったのが京大の総合人間学部でした。このときはまだ、「さすがに私が京大なんて…」と思って、自分の志望校として考えることはなく、その後なんとなくの気持ちで理系に進みました。しかし、自分が理系学部よりも文系学部に興味があったり、大学進学のタイミングで自分の学ぶ学問の幅を狭めてしまうことに抵抗があったり、また、先生に進路相談で京大をすすめられたこともあって、「総人に行きたい!!!」と再び考えるようになりました。ほかにも、高3の夏に京大を訪問したときに、近くに川があったり、めっちゃ平地だったり、飲食店がいっぱいあったり、広大な敷地で学べる環境にひかれて、さらに京大に入りたいなという思いを強めました。
●受験勉強の仕方
一年浪人しているので、その経験をふまえてお話させてもらいます。まず、問題が解けたか解けなかったかが大事なのは本番だけです!本番まではその問題から何を得られたかの方が圧倒的に重要です!例えば数学なら、この系統の問題を解くにはこの定理を使うとうまくいくこともあるんだな。みたいに。これを意識するだけで、目の前の問題に対する考え方が変わるし、解けなくて「全然解けないどうしよう…」みたいに考えることも減ります。あと、自分のケアレスミスを記録しておくことをおすすめします。模試前とか本番前に見ておくと、ケアレスミスはかなり減ります。さらに普段の問題でケアレスミスしたときも、「また自分のミスの傾向見つけちゃったラッキー☆」みたいに考えられるようになります。あと、総人は驚くほど二次配点重視です!私は現役のときこのことをほとんど意識せず、冬に共テ対策だけしまくり、二次を解く力が消え、二次の点数があまりにもとれなくて落ちました。浪人期はこの反省を活かして、共テの直前でも、共テ対策と並行しつつ二次対策もしっかりしていました。本当に共テと二次では使う頭が違うような気がします!一日に一回京大数学を一問解くとかでもいいので、共テ前も二次試験対策を忘れないように!
●受験生に向けて一言
受験はとても大変ですけど、その前に、高校生の人たちは受験勉強にとりつかれすぎず、高校生活を謳歌してください!私は部活動にものすごく力をいれていました。特に高校三年生の夏の半分は部活ばかりであまり受験生らしい夏を過ごした記憶はないのですが、今でも当時の部活のメンバーと仲がよく、本当に未来の自分の糧になる良い経験をすることができたと思っています。高校生活は今しかできないです!卒業するときに笑顔で「たのしかった!」といえるように今を全力で過ごしてください!浪人生も現役生も最後まで成績は伸びます!自分を信じて最後まであきらめずにやりきってください!
文学部
文学部
ペンネーム:やまのた
●京大を目指したきっかけ
京大を志望校として初めて意識したのは、中学生の時に京大出身の作家・森見登美彦さんの著作を読んだ時です。森見さんの描き出す京都という土地柄と自由な校風の京大に惹かれ、ぼんやりとした憧れと興味をもつようになりました。 具体的に京大を目指したのは高2からです。やはり最も興味があるのは京大だということと、とりあえず目標は高く設定しておこうというどちらかというと消極的な理由でした。
●受験勉強の仕方
私は部活を引退した高2の1月頃から受験勉強に本腰を入れ、それまではテスト期間の勉強のみにとどまっていました。
私が受験勉強を振り返って後悔するのは、「慎重になりすぎて何事も取り組むのが遅かった」ということです。目の前の課題や苦手科目に押し潰され、つい「これを終わらせてから…」と思ってしまい、時間をかけるべき社会科目や過去問に手をつけるのが遅くなってしまいました。やるべきことに優先順位をつけるのは大事ですが、一つのことにかける時間が偏りすぎないように他の科目に取り組んだり新しいタスクに挑戦したりする勇気が必要だったなと思います。個人的な意見を言わせていただくと、社会科目は夏中には一周終わらせ、過去問は春夏頃から定期的に解くのが理想です。
一方で私が受験勉強を振り返ってやってよかったと思うのは、「取り組む参考書の数を絞って繰り返し見返した」ことです。受験期を通して書き込みを続けた参考書には愛着がわき、「これを見るだけで必要なことがすべてわかる」という安心感と自信につながり、本番直前に平常心を取り戻すために役に立ちました。
京大の試験に即したことを言うと、特に現代語訳や和訳では、問題文から概して理解したことを自分の言葉で書き直すよりも、問題文にある要素をとり漏らさず丁寧に解答に含めることが求められていると思っているので、助詞や細かい文法事項にも敏感に反応できるように心がけました。
●受験生に向けて一言
受験勉強は本番までに自信をつけるプロセスだと思います。本番ではどれだけ自信をもっていつも通りの状態で臨めるかがとても重要です。しかし同時に知っておいてほしいのは、本番当日に苦手な分野や不安があるのは当たり前だということです。自分ができる範囲でのベストをたたき出せば絶対に結果は応えてくれます。
最後に、みなさんには「頑張ってください」という言葉よりも「頑張っていますね」と言葉をかけたいと思います。なんだか上から目線に聞こえますが、これは私が受験期に何度も友達と自分自身にかけてきた言葉です。努力している受験生はかっこよくてまぶしい存在です!自分を褒め続けて受験期は乗り越えましょう!みなさんと京大でお会いできることを楽しみにしています。
教育学部
教育学部
ペンネーム:ゆう
●京大を目指したきっかけ
私が京都大学を目指したきっかけは、高校1年のときの面談で先生に京大も目指してみたらどうかと言ってもらったことで、当時は漠然とした憧れはあっても自分が行けるとは全く思っていませんでした。しかし高3になり本格的に志望校を決めるというときに、もともと心理学に興味があったこともあって、目指すならできるだけ良い環境で自分のやりたいことをできる大学を目指したいと思い、京都大学を志望することに決めました。また、オープンキャンパスに行った時のその自由な雰囲気や先輩方の楽しそうな雰囲気も決め手の一つでした。
●受験勉強の仕方
私は家で勉強することが全くできなかったので、普段は通学の電車や学校についた後の時間で勉強していて、高3の夏に塾に入り本格的に受験勉強を始めた後も、家でできない分塾で集中して勉強するように分けて取り組んでいました。受験は長期間でストレスもたくさんたまる分、自分に合う勉強法で進めていくことはとても大事だと思います。実際の勉強では、夏の間に基礎を固めて、ある程度固められた時点で過去問を解いて最終的に自分がどんな問題を解けるようになりたいのか把握しておけたことがよかったです。最初は全く解けませんでしたが、繰り返し解いていくことでだんだんと力がついていくと思います。自分は数学が苦手だったので特に数学に力をいれて対策していました。また、受験期間中は長く感じますが私は共テ前ぐらいから時間の進みが一気に早くなったように感じました。当日も単語などが完成しきらなかったり演習量が足りないまま本番になだれ込んでしまったので、みなさんは自信をもって本番当日を迎えられるように余裕をもって頑張ってください。
●受験生に向けて一言
私はだいぶぎりぎりのなかで京大を受けていて、模試の判定もEからBまでまちまちで、特に共テ後の最後の模試でE判定だったときには落ち込んだし焦りましたが、もうあとがない状況で切り替えて直前期に頑張れたことが大きかったなと思います。自分もそうでしたが、成績が伸びず焦りや不安のなかで長い受験期間を過ごすと思います。ですが、自分の実力の伸びが表れてくるのにはすごく時間がかかります。不安のなかでも最後まであきらめずに頑張ってほしいです。応援しています。
法学部
法学部
ペンネーム:眠気
●京大を目指したきっかけ
高校が自由な校風だったこともあり、同じような雰囲気の大学に進学したいと思っていました。また、一人暮らしをしたいと中学生のときから思っていたため、関東圏に住んでいた僕は高2の冬ごろに京都大学を意識し始めました。加えて、法曹を志望していたので京都大学法科大学院の司法試験合格率が全国トップクラスであることが決め手となり、この大学を志望するに至りました。
●受験勉強の仕方
受験は積み重ねが重要だということに尽きますが、京大法学部受験に対する自分なりの戦略について主に書いてみようと思います。
高3の6月に部活を引退したのち、本格的に京大対策に取りかかりました。引退後、まずは法学部で重視される英語の対策に力を割きました。京大の英語は長い和訳と英作文が多く、早めにこの変わった形式に慣れておいたのが良かったと思います。また、過去問を解いた1週間後にもう一度解きなおす、といった復習のサイクルはかなり自分の力になりました。
自分は数学が安定しなかったので、間違えた問題をまとめたノートを作り自分の苦手分野をあぶり出すことを意識しました。夏から秋にかけて苦手分野のあぶり出しと復習を行い、11月ごろから過去問を解き始めました。はじめは全く歯が立ちませんでしたが、腐らずに何度も復習を繰り返すことで少しずつ成長を感じられるようになりました。
僕が一番苦労したのは国語、特に現代文でした。模試の偏差値は一度も50を超えたことが無く、学校での演習も常に平均点を下回っていました。いくら演習と復習を繰り返しても現代文の成績は全く伸びず絶望したのをよく覚えています。そこで12月ごろからそれまで現代文にあてていた時間の多くを古文に割きはじめました。というのも僕の古文の成績は勉強量と成績がある程度相関していたからです。それからの現代文の対策は演習を繰り返すことに重点を置き、減点されない書き方を模索するようになりました。
社会は世界史を選択していたので、京大で出題されることが多い東アジアの歴史を重点的に対策しました。ただ他の科目と比べて世界史を疎かにしていたせいで満足に論述対策ができずに受験本番をむかえました。暗記科目の対策は計画的にやるのをおすすめします。
●受験生に向けて一言
国語に最後まで苦しめられたと書きましたが、開示での国語の点数はかなり良かったです。逆に重点的に対策したつもりの数学の結果は満足いくものではありませんでした。このように本番では何が起こるか分かりませんし、良いほうに転ぶか悪いほうに転ぶかは予測不可能です。しかし自分なりの戦略を持つことが合格への近道だと思います。
心から応援しています。本番まで全力で走り抜けてください!!
経済学部
経済学部:文系
●京大を目指したきっかけ
僕の高校は関東にあったので、周囲の多くは東大を目指すという環境でした。しかし、関東で育った僕は、大学時代は全く知り合いのない土地で一人で生活してみたいという思いが起こり、東大と京大、一橋で悩んだ結果、京大を目指すことにしました。京大は学問研究に強いという理由も決め手になりました。また、学部に関しては社会哲学なども学んでみたいとの思いで文学部も考えてみましたが、自分の目標である、日本の社会的立場の弱い人を救うという目標を達成するには経済と向き合った方がいいのではないかということで経済学部を志望することにしました。そしてこれはあまり大きな声では言えませんが、自分は数学と世界史が得意だったのでその二教科の配点が大きかったということもありました。配点で学部を決めるのは決して良いことではありませんが、まず京大に入るのが最優先という場合もあるでしょうし、何より自分の強みが出せる配点であったことが、追い込まれた際も支えとなることもあるので、人それぞれだと思います。
●受験勉強の仕方
前述の通り、自分は数学と世界史に得意で、英語と国語に苦手意識がありました。しかし、第一回京大模試ではその数学で1完0半に倒れ、総合でもD判定でした。敗因としては、英語の勉強に時間を割きすぎて、数学に手が回っていなかったことです。また、当時勉強していた英語に関しても非効率的な勉強をしており、京大英語はおろか共通テストでも全く点は取れていませんでした。その頃は世界史の知識も古典文法もあいまいで、得意教科なしという危機的な状況でした。しかし馴染みのあった二科目で、数学で2冊問題集を決め、その中の問題を一個一個理解できるまで毎日やったこと、世界史は「自分は歴史が得意」という思い込みを捨てて淡々と教科書と単語帳の読み込みを行ったことで、数学と世界史に関しては7,8月とじわりじわりと上がっていく感覚になりました。二次試験550点の中での自分の核がつかめたことで英語、古典にも腰を据えて取り組めるようになり冠模試は夏以降上がっていきました。自分の受験においては①得意、好きを伸ばすことで精神的余裕が生まれて苦手科目へのハードルが下がることもあること②継続することで初めて理屈を超えた“感覚”が得られること、が鍵となりました。
●受験生に向けて一言
結論を言うと、試験問題というのはただの数問の集合に過ぎず、意外な人が落ちたり受かったりするものです。自分も自分の努力がわずか数問で決まる(特に数学)ことに強い不安感を覚えていました。しかし、自分の塾では「勉強の不安は勉強でしか払拭できない」と言われていました。自分も心が折れそうになった際は勉強をひたすらにやることで、「たとえ落ちても無駄にはならない一日を過ごせた」と思うようにしていました。後輩の皆さんの受験勉強が、たとえ結果がどうであれ京大合格に向かって歩みを止めないものになることを願います。
経済学部:理系
ペンネーム:ちゃみ
●京大を目指したきっかけ
私のいた高校では、二年生に上がる時に文理選択を行います。数学に自信のあった(そして英語ができなかった)私は、安直に理系を選びました。
しかし、高二夏に、理系が一般的に選ぶような進路が、自分の肌に合わないことに気づきます。医歯薬系へ行く志はなく、理工系を選ぶほど理科が好きではなく、高校数学が得意なだけで、大学数学科での厳密な数学を究める気もないといった状態で、志望校選びに行き詰まります。そんな中、京大経済学部理系方式を見つけました。 経済学は文系のイメージが強く、理系高校生の視野に入りづらいですが、実際は数式を用いたモデルに経済現象を落とし込み、数学的に分析を行う学問で、数学力がかなり有用です。この点で経済学に興味を引かれ、京大理系経済が第一志望に定まります。
●受験勉強の仕方
※数学でかなり稼げる自信があった受験生の勉強法であることには注意してほしいです
数学については、幅広い解法に触れること、そして知っている解法をいかに早く引き出せるかを大事にしていました。京大数学は誘導が少ないタイプなので、知っている解法に素早く落とし込むことができると、大きなアドバンテージになります。私は、少々高難度の問題集や京大過去問(文理問わず)を使うことで、解法収集と、それを引き出す訓練をしていました。
英語はずっと苦手で、しかも中高一貫の中だるみも相まって長い間英語の勉強を避けていましたが、致命的な点だけは取らないように、英作文を重点的に対策しました。使える表現を参考書で増やし、京大英作の特徴である直訳不能な日本語を、知っている英表現が使える日本語に置き換えるといった訓練をしました。長文に関しては、単語力も解釈力も平均的合格者からは大幅な遅れをとっていたと思います。受かったから良いですが英語における積み重ねは本当に大事です。
共テについては、二次と頭の使い方がまるで違うので、頭を共テ仕様にするべく12月を共テのみの月にすると決めて、特に、共テのみの教科と、苦手な英語Rの対策をしました。予想問題を解いて参考書等で復習することを繰り返しました。共テが終わったらさっさと二次対策に戻ることもまた大事です。
●受験生に向けて一言
試験前の心構えですが、「この教科、単元に自信がない」「自分は京大に受かるレベルにあるのだろうか」といったネガティブな考えは捨てて、「この教科に圧倒的自信がある」「自分なら受かるはずだ」といったポジティブなマインドを持つとよいです。私は、数学に圧倒的自信を持って本番に挑めたことが、一番の勝因だと思っています。周りに焦っている受験生がいたりすると、どうしても流されて焦ってしまいますし、その焦燥感が勉強の原動力になったりもしますが、試験直前までそんなに焦って勉強していたら、本番で十分に実力が発揮できないだけなのじゃないかと私は思います。入試は勉強量が多い人から受かっていくといった単純なものではないですから、受験生の皆様には勉強だけに気を張るのではなく、メンタル維持にも気を配っていただきたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。皆様の受験を、陰ながら応援しています。
理学部
理学部
ペンネーム:マヨネーズ
●京大を目指したきっかけ
私が京都大学を目指したきっかけは、昔祖父に連れられてキャンパスを訪れたことだ。そこで私は歴史のある建物やレベルの高い授業に魅了された。と、いうわけではない。当時10にも満たなかった私にとって最も魅力的だったのは時計台にあるフランス料理店であった。その料理のあまりの美味しさに衝撃を受けた私は、安易にも自らの人生設計図に京大進学の四文字を加えたのだ。数ある学部の中で理学部を選んだのは理学科のみの1学科制であることが大きい。私は物理も化学も好きで、大学受験時にどちらか一つに道を定めてしまうのはあまりにも悩ましかった。そこで、1・2回生の間は幅広い分野を学び、3回生で進む分野を決定するという理学部のシステムを活用することにしたのだ。
●受験勉強の仕方
受験勉強の仕方については残念ながらあまり語れることがない。私が通っていた高校は毎年一定数京大合格者を出しており、先生方の中に京大受験対策のベテランが複数人いらっしゃったのである。正直なところ、私は彼らの用意した特別対策授業や資料におんぶに抱っこであった。強いていうならば、苦手分野をさっぱり諦めるか、さらに努力するかで分別しておいたことだろうか。約12年の学習経験から、私は自分のできることとできないことをよくわかっていた。努力してもどうにもならないものよりも、努力でなんとかなるものにリソースを割く方が効率がいいのは当たり前である。時には諦めることも大切なのだ。
●受験生に向けて一言
最後に受験生の皆さんへ。受験期にはたくさんしんどいことがあるでしょう。悩んだり苦しんだりした時には周りを見渡してみてください。自分と同じように苦労している人を見ると、なんだか同情心と共にやる気が出てくるものです。皆さんが京都大学に入学する日を心待ちにしています。
薬学部
薬学部
ペンネーム:マシュマロ
●京大を目指したきっかけ
もともと薬学や医学に興味があったことに加えて、化学や数学が好きで、なんとなく薬学部に行きたいと思っていました。高校2年生の夏に、京大のELCASに参加したことで、実際に研究されている様子や、その方法などの一端を体験することができ、なんとなく行きたい、から、薬学部を目指そうと思うようになりました。医学にも興味があり、医学部も少し考えましたが、薬学と医学は全く別の分野ではなく、また、薬から病気にアプローチすることに魅力を感じ、高校の先生との面談の後、秋ごろに本格的に京大の薬学部を目指すことを決めました。
●受験勉強の仕方
私は公立高校に通っていたのですが、各々が高い目標を持って学んでいたので、同級生と一緒に頑張ろうと思って勉強に励んでいました。1、2年生の間は部活動が忙しく、平日の勉強時間はあまり多くはなかったし、部活動の本番が続く時期は土日もあまり勉強できていませんでした。そのような中でも、数学の基礎基本の復習を毎日することや、電車に乗っている時間に英単語や古文単語を覚えることは意識していました。また、すきま時間や土日の空き時間を使って、一週間のうちに、その週に学んだことを一通り復習できるように計画を立てながら勉強していました。高校3年生になると、部活動がいったん終わったので、あまり集中できていなかった日本史の勉強を進めるとともに、化学や物理の復習を行いました。部活動の引退、また、文化祭の終わりとともに、きっぱりと勉強に切り替えることができたと思います。京大の過去問については、数学、化学、物理は11月から、英語は12月から、国語は共通テストが終わってから始めました。高校の授業で2次試験対策があったので、その内容の復習を徹底していました。
●受験生に向けて一言
私は、2次試験の試験中に物理の公式がわからなくなり、1つの大問を1問も正しく解くことができませんでした。そこで、どんなに応用を学んでも、基礎基本が整っていなければ、意味がないということを突きつけられました。受験生の皆さんには、難しい内容になっていったとしても、基礎基本の確認を怠らないでほしいです。そして、本番は、何があっても諦めずに一つ一つの問題に向き合ってほしいです。もちろん勉強に向き合う時間も大切ですが、高校生活でしかできないこともたくさんあるので、行事や部活動など、やりたいことを全力で楽しんでください。全力で楽しんだ時間は、受験勉強を頑張るエネルギーに変わります。勉強中に辛いときにも、楽しかった思い出を糧に、もう一度勉強に向き合うことができると思います。皆さんが、行きたいと思うところへ進学できるように、陰ながら応援しています。
医学部
医学部:医学科
ペンネーム:恭一浪
●京大を目指したきっかけ
京大に興味を持ち始めたのははっきりとは覚えていませんが高2ごろだったと思います。当時はそこまで思いは強くなく「東大の性格が自分に合わなそうだな」と感じていたのと通っていた中高に似た自由な雰囲気の校風らしいと聞いたことで何となく志望していました。この思いは高3の8月に京大を訪れ雰囲気を肌で感じたことで固いものとなりました。同時に医師になりたいという気持ちも芽生えていたので京都大学と医学部の共通部分ということでここを目指し始めました。しかし成績が芳しくなかったので広島大学医学部、京都大学農学部とも共テ後まで迷いましたが「ここで妥協したら一生後悔する」という思いで特攻しました。結果は不合格でしたがこの決断を悔いたことは一度もありません。まさに「やらない後悔よりやる後悔」ですね。
●受験勉強の仕方
自分は一浪して入学したのですが、現役時はずっと同じ場所で勉強していてあまり集中することができなかったので、浪人時は定期的に(約2か月ごと)に勉強場所を変えるようにしていました。
また、世間でも言われていることですが、基礎が終われば過去問には早く触れ始めたほうがいいと思います。消費が嫌な人は25か年などを買って昔のから消費していけばいいと思います。京大は慣れればそこまで難しくはないものの独特なテイストの問題が多いので、できるだけ早くその空気感に慣れていくことが京大合格のカギだと思います。浪人期に一気に成績が伸びて安定しだしたのは慣れが一番大きい思います。
また、二年間の受験勉強の中で最も重要だと感じたのは「継続して走り続けること」です。現役時は夏休み頑張りすぎて秋模試前にサボってしまったり共テ前に頑張りすぎて一番重要な2月にサボってしまったりし、これが不合格に直結したと感じました。逆に浪人時は現役時よりもカラオケやUSJなどに行ったりしましたが、一年間一定のペースを保って勉強し続けることができたのが合格の要因だと思っています。なので特に怠惰気味な人には頑張りすぎて勉強時間に波を作るのではなく“適度に”息抜きをしながら一定のペースで走り続けることを目標にしてもいいと思います。
●受験生に向けて一言
これを読んだ皆さんと京都で会えるのを楽しみにしています!無理をしすぎず走り切ってください!皆さんの受験が「やらない後悔よりやって大成功」となることを心より願っています!
医学部:人間健康科学科
ペンネーム:ふゆ
●京大を目指したきっかけ
京都大学を目指す理由は人それぞれだと思いますが、私の場合は何か頑張れる目標が欲しいからというものでした。今思うとくだらない理由ですが、それでも好きなものもやりたいこともない自分が進路を選ばなければいけない時期にきたときに、とても悩んで決めた自分にとって大事な土台でもあります。やりたいことを見つけられる環境がいいという思いや、当時の自分が羨ましいと思っていた何かに真剣に取り組める人になりたいという理由で自分にとって難しい大学がいいなどの考えから、最終的に高校3年生の夏に目標を京都大学に決めました。
●受験勉強の仕方
まず勉強する習慣がない人はそれを身につけるところから始まります。私は一年くらいかかりました。そのあとは問題を答えを見ながら解いて、だんだん見る頻度を減らして自力で解けるようにするというような勉強をしていました。受験を通して特に苦しんだのは、最初の勉強する習慣を身につけるまでと、浪人時に自分の欠点に向き合ったことです。勉強する習慣が身につくまでは自分が今までにどれだけ他の同級生と差をつけられていたのかと毎日後悔していたし、自分の欠点と向き合うことはいうまでもなく辛いことでした。欠点と向き合うと言っても必ずしも直せるものではなく、例えば私の場合は英単語を覚えるのがどうしても苦手で、結局入試本番までに単語帳の最初の10ページくらいしか覚えられませんでした。その場合自分はなんでできないんだろうという気持ちを入試当日まで抱えることになりますし、実際私もそうで、当日、周りの受験生の単語帳や参考書はボロボロなのに、自分だけ綺麗でとても恥ずかしかったのを覚えています。個人的な考えですが、勉強に限らずちゃんとしている人にはちゃんとしている理由があって、それは目標とかの大きな理由ではなくて、最初は親に怒られるからとか、友達がいるからとか、途中で寄り道できるからとか、そう言った些細な理由で始めた習慣が当たり前として身についているからで、そういう昔からの小さな理由が積み重なって「ちゃんと」ができていて、だから今からの頑張りだけではどうしようもないこともあるとおもいます。もちろん頑張らなければいけない時もあるけれど、でもうまくいかないことをすべて努力が足りないからだとは思わないで欲しいし、何か始める時はまずそう言った小さな理由を見つけるところから始めて欲しいです。覚悟を決めるというよりも、一歩一歩当たり前に近づいていくような感覚が大事だと思います。
●受験生に向けて一言
受験生の皆さん、大学は楽しいですよ。矛盾するようですが、どこにでもこの人がいるから、あるいはこれができるからここに入ってよかった、むしろここじゃないとダメだったと思えるような場所はあるし、だからどこの大学に行ってもきっと楽しいです。そしてその上で、今これを読んでいる皆さんが、楽しいと思える大学生活を、京都大学で送れることを心からお祈りしています。
工学部
工学部:地球工学科
ペンネーム:らて
●京大を目指したきっかけ
私が京都大学を目指したきっかけは、高校二年生の夏休みに高校の行事で京大を訪れたことです。その時に感じた京大の静かな雰囲気、そしてすれ違う京大生の楽しそうな様子を感じ取り、自分もここで楽しい大学生活を送りたいと強く感じたことをよく覚えています(実際、周りの京大生には大学生活をしっかり楽しんでいる人が多いように感じますし、私自身もかなりエンジョイしています)。三年生、そして浪人生になってもその思いが消えることはなく、二年連続で京大を受験し浪人で無事合格しました。個人的にはこれぐらいでも京大を志望する理由としては十分だと思います。現時点で志望動機がはっきりしていない方もとりあえず京大を目指していたらそのうちはっきりした動機が見つかるかもしれないし、見つからなかったとしても目指し続けるうちに京大に行きたいという思いが強くなっていくので心配する必要はないと思います。
●受験勉強の仕方
浪人しているのもあってあまり偉そうなことは言えませんが一つだけ。まずは焦らずに基礎をしっかり固めてください(特に二年生までは新しく習った範囲の基礎をその都度完璧にすることを最優先にしてください)。例えば数学の場合で言うと青チャートやプラチカぐらいのレベルです。京大の入試は確かに難しいし少し独特ではありますがそれは天才的なひらめきが必要という意味ではなく、いかに基礎知識を組み合わせて応用できるかを問われているのだと思います。きちんと標準的な入試が解ける基礎力が身についているのなら、過去問で京大の形式に慣れる練習は2、3か月前からでも間に合うと思います。
●受験生に向けて一言
受験勉強にしんどいイメージを持っている方もおられると思いますが、どうせやるのなら最後まで全力でやりきってほしいです。合格か不合格かに関係なく、受験まで走り切った経験自体がこれからのあなたの自信になると思います。個人的にはあまり合否という結果だけにこだわりすぎることなく、自分を成長させる機会として受験勉強を頑張ってほしいです。どれだけ頑張っても合格率を100%にすることはできない以上、合格がすべてだと思って勉強を続けるのはかなりつらいと思いますよ。また、受験生だからといって勉強ばかりするのではなく、高校での友達との時間なども大切にしてほしいです。時には周りの人の力を借りながら、楽しんで一年間を乗り切ってください。応援しています。
工学部:建築学科
ペンネーム:ドーナツ
●京大を目指したきっかけ
率直に、自分の受験前の状況を色んな視点から見た結果、京都大学の受験が最善の選択だったからです。以下、考え方についてまとめようと思います。
僕は幼い頃からの経験を振り返って、計画事と街づくり(おもちゃ、マイクラなど)が好きで、人との関わりについても興味がありました。そういった興味に対応する分野は建築設計や都市計画だと思い、この文理融合的な性質から、まず総合大学を目指したいと思いました。そして設備・教授陣が充実し、交換留学制度も豊富で、学費の安い国立を前提としました。次に、若い1年を受験勉強に捧げることと大学のランクアップを天秤にかけ、現役で合格することにこだわりました。結果、これらの条件を満たす京都大学を最終的に志望しました。また、京大建築は一回生のうちから学部として独立しているため、一回生のうちから製図室を与えられます。そのため、一般教養科目を受講しつつも、製図課題といった建築味のあることに没頭する環境が得られることも、個人的には大きなポイントでした。結果、プレッシャーがかかりがちな直前期にも、モチベーションを切らさずに受験勉強をやり切ることができました。
●受験勉強の仕方
大事なのは、自分の勉強の穴をなくすことです。それには、問題集等でわからない問題に出会った時、不明点について教科書までさかのぼるといった地道な積み重ねが役に立ちます。自分の行きたい大学を目的地にした参考書ルートだけをたどるだけでなく、同時に自分の不明点を自覚して、それらを埋めていくことで勉強は成立すると思います。
結局、「自己認知」が根底にあるのでしょう。
自己認知は、絶対的なものではありません。新しい人と出会い、新たな価値観に触れた時、自分の認識も少しずつ変わっていくでしょう。しかし、現時点で満足に考え抜き、それに自信を持っているということが大事なのだと思います。進路選択や勉強も同じです。今が不安でも、現時点で自分を俯瞰し、穴のないベストな勉強ができたなら、それが自信の根拠になると思います。ひとたび自信を持てば、モチベーションが上がり、成績も上がり、自信をつけるというポジティブなサイクルが回りだすことでしょう。
●受験生に向けて一言
僕もそうだったのですが、受験期は「志望大学に受かる」ことが至上命題になるあまり、視野が狭くなりがちです。適度に息抜きをしながら、先述の考え抜く・やり抜く経験を大切にしてほしいなと思います。
受験生の皆さん、ぜひ、最後まで走り切ってください。応援しています。
工学部:物理工学科
ペンネーム:ふくよろ
●京大を目指したきっかけ
私が京大を目指したきっかけとして、まず通いやすかったというのがあります。家の経済的事情で私立への進学は難しいので国公立の大学にしたいと考え、できるなら近畿の大学に進学したいと考えていました。その中で有名な京都大学に進学したいと漠然と思って受験しました。その中でなぜ物理工学科を志望したかというと、進学後に自分の勉強したい分野を入学後に決められるからです。私は当初、電気電子工学科を第一志望としていたのですが、浪人中に興味が薄れ自分が何を勉強したいのかわからなくなりました。そこで自由度の高い物理工学科に行こうと考えたのです。
●受験勉強の仕方
恥ずかしいことに私は現役時に受験生とは思えないほど勉強時間が少なかったので数学が2割しかとれず落ちてしまいました。そのため私の浪人時の勉強法について話したいと思います。浪人時は前期の間は予備校のテキストを中心に復習し、余った時間で過去問を進めていくというやり方をしました。何せ浪人生ですから基礎に欠落があると考え前期の間は過去問をあまり進めずテキストをしっかりやりこみ基礎固めをしました。夏期講習の期間に入ると京大対策の講座や特講シリーズの授業を受けました。今思えばこの講座で理科や数学の力がグンと伸びたと思います。後期からはテキストの復習の比重を少し減らし、共テや京大対策の演習時間を増やしていきました。共テに関して私は高得点をとれる自信があったので本格的に対策した12月までは日本史と情報以外ほとんど勉強しませんでした。年末からは共テ一本で対策し、共テが終われば京大の過去問の一年分を一日でする生活にしました。特に二次試験前は、通学時間はいつも英単語帳を読んでいました。工学部志望なので国語の配点はとても小さいですが理系の古文は簡単であることが多いので現代文より古文を重点的に対策しました。二次試験直前はあえて焦らず苦手だと思う問題をじっくり確認して試験に臨みました。
●受験生に向けて一言
大学受験はとてもつらいですが、合格発表の時に自分の番号を見つけ努力が報われたと感じる瞬間は何にも代えがたいです。皆さんもそんな体験ができるように頑張りましょう。皆さんが笑顔でこの京都大学に入学してくることを心からお待ちしております。
工学部:電気電子工学科
ペンネーム:カルボン
●京大を目指したきっかけ
私は、小学生のころから京都にある某ゲーム企業に就職したいと考え、そのゲーム企業について調べてみるとその企業には京大出身者が多いと知り京大を目指し始めました。その企業にはプログラマーとして就きたいと思い、またそれに加えて私が高校生のときに情報Ⅰが施行されたために情報の講師等にも取り組んでみたいという思いもあり工学部情報学科を第一志望としていました。しかし、工学部には第二志望の学科まで選択することができる制度があり、また電気電子工学科でも情報学を学ぶことができると知ったため電気電子工学科を第二志望にしました。
●受験勉強の仕方
私が受験勉強を本格的に始めたのは高校3年生の春でした。3月までには高校範囲の基礎の学習を終了し、4月から8月までの間で共通テストの過去問を10セット分解きました。さらに、6月頃から京大二次試験の対策として数学の過去問が分かりやすく解説されている参考書を買い、工学部で配点が大きい数学の対策を徹底的に行いました。また、夏休みを活かして10年分の二次試験の過去問に取り組みました。そして、9月頃からは予備校が私の苦手分野を分析してそれに応じた過去問・模試のバックナンバーを提供してくれるプログラムで勉強していました。
このような感じで1年間勉強していましたが、ポイントを3点ほど紹介します。
①誰もが同じことを書くかと思いますが、基礎基本は年がら年中繰り返し徹底しましょう。私も二次試験直前までずっと英単語帳や古文単語帳を読んでいました。特に、数学と理科は「どうやって基礎基本徹底すりゃええねん…」と悩みがちになってしまいますが、積分の問題が出るアプリや理科の知識をチェックするアプリなどスマホのアプリを利用するのも1つの手だと思います。
②過去問は早め早めにやりましょう。意外と量が多いです。後で後でといって結局十分な量の過去問解くことができなかった方を見たことがあります。
③配点を意識しましょう。例えば2025年度入試の京大工学部の共テの配点は1025点中225点でしたが、その中でも英語・地歴公民・情報の配点が50点となっていました。共テにおいてはその3科目に重きをおいて取り組むようにしていました。
●受験生に向けて一言
特に工学部・農学部向けの話になりますが、第二志望以降の学科も検討し、入試では第二志望以降の学科もしっかり志望すると良いと思います。私自身もスライド合格で第二志望の電気電子工学科に入学することができました。正直、京大入ることができたらあまり変わらないかな、と思っています。
最後に、受験勉強をしていると長すぎる共テ模試、体力も精神も削られる京大模試、なかなか思うように解けない京大の過去問などに潰されそうになるかと思います。そんなときは京都の観光名所の写真などを見るとモチベーションが上がりオススメです。このように、辛くなったら京大に入学した後のことを考えてみてください。
みなさんが入学するのをクスノキと一緒に待っています!頑張ってください!!
工学部:情報学科
ペンネーム:ロイス
●京大を目指したきっかけ
私が哲学や物事の本質について考えることに興味を持ち始めたのは、小学校高学年の頃である。哲学に関する本を読み、自分の考えと照らし合わせてみたり、そこからさらに思考を深めたりすることが好きであった。しかし、小中学生の頃は、哲学の話を友人に持ちかけても「よく分からない」と返されることが多く、自分の関心について思うように語れないのが残念であった。
そうした思いから、より多様な価値観に触れ、知的な会話ができる環境を求めて、学区で最もレベルの高い高校を目指し、無事合格した。ところが、そこでも勉強はできるものの、哲学的な話題を深く共有できる相手はなかなか見つからなかった。
だからこそ、大学では、自分の興味を自由に語り合える仲間がいる環境で学びたいと強く思うようになった。京都大学は、西田幾多郎をはじめとする著名な哲学者を輩出しており、哲学の分野でも高い評価を受けている大学である。さらに、学生の学力レベルが非常に高く、自分の考えをしっかり持ち、主張できる人が多いという印象があった。そうした環境であれば、自分の関心に共鳴してくれる仲間と出会えるのではないかと感じ、私は京都大学を目指すことを決意した。
●受験勉強の仕方
私は浪人して京都大学に合格したわけであるが、ここでは基礎と知識の重要性を強調したい。現役の頃は焦って、いきなり応用問題や過去問に手を出していたため、最後まで全く伸びなかった。浪人してから予備校で基礎の内容から詰め直したところ、思いのほか抜けが多いことに気づかされた。基礎とは「簡単」という意味ではなく、「重要」であるという意味である。
例えば数学の三倍角の公式や和積の公式といったものがあるが、「こういうのは覚えるのではなく、その場で導出するものだ」といった話を聞いたことがあるかもしれない。だが、そうした考えは今すぐ捨ててほしい。これらの公式や基礎問題の結果(答え)は、頭に入っていなければならない。というのも、応用問題の中には、道筋が見えてこないものも多く、その際に一から導出していては時間が足りない。試験時間はもともと短く限られているのだから、そういった時間は削減し、少しでも思考や清書の時間に回すべきである。
私は数学に関しては、チャートの例題をすべて覚えた上で、準基礎的な事項も暗記した。物理や化学についても、予備校のテキストの基礎問題を徹底的に暗記し、その解き方の流れと結果をすべて頭にたたき込んだ。その結果、試験当日はほとんど頭を使わずに問題を解くことができた。結局、問題が難しくて解けないというよりも、応用問題とは基礎問題の集合であり、その中のどこかに欠けがあるから解けない、というケースの方が多いように思う。基礎は99%ではいけない。100%でなければならないのだ。
●受験生に向けて一言
焦らず、確実に基礎をマスターしよう。周囲の人が難しい問題を解いているのを見て、自分が遅れているのではないかと不安になる気持ちは分かる。しかし、そうして基礎が99%で止まってしまっては意味がない。基礎力があれば、どんな問題も一刀両断できる。基礎を積み重ねた自分を、最後まで信じ抜いてほしい。
工学部:理工化学科
ペンネーム:あるみ
●京大を志望した理由
私が京大を志望したのは、高三の夏からです。周りが皆志望校の大学別模試を受けるシーズンになった時、自分の学力的に東京工業大学か京都大学が志望校の選択肢としてありましたが、周りに東工大志望が多いから、と焦って京大を選びました。受験勉強に大層な志望動機はいらないと思います。その大学を目指して勉強しているうちに受かりたい気持ちは強くなっていきます。名前がかっこいいとか楽しそうとか適当な理由でも自由に志望校を決めてほしいです。
●受験勉強の仕方
高1、2では英単語、英文法、数学に勉強の9割を費やしていました。机に座っただけの日も、二時間くらいやった日もありますが、毎日勉強をしようとはしていました。
高三も志望校が決まるまではこれまでと同じように勉強し、志望校が決まってからは京大に向けた勉強をしました。具体的には英文解釈の勉強を加える、古文漢文の勉強を始める、理科の問題演習などです。1月になると、共通テストが近づいてきます、工学部は社会の配点が大きいので、他教科を完全に捨てて2週間倫政にオールインしました。共通テストが終わると同時に、過去問演習を始めました。今までの勉強から完全に過去問演習にシフトするか、少し過去問演習を入れる、という形にするか悩みましたが、私は後者を選び、最終的に5年分くらい遡りました。
●受験生に向けて一言
最後に、当時も、今振り返っても、受験期は結構楽しいものでした。それはひとえに一緒に勉強してくれた友人のおかげです。互いの志望校の問題を解いてみたり、私大の情報を交換したり、問題の悪口を言ったり、休憩に遊んだりして気づいたら二次試験であっという間でした。皆さんも時間を大切に、楽しんで受験を頑張ってください。
農学部
農学部:応用生命科学科
ペンネーム:えでぃ
●京大を目指したきっかけ
僕が京大を明確に目指し始めたのは高三の夏ごろでした。僕は北海道の有名ではない高校出身で、京大の先輩などいなかったのでずっと北海道大学を目指していました。ただ、予想外に成績が伸び高三の6月には北海道大学には合格できるだろうという状態になりました。そこで僕は視野を広げようと思い、種々の大学について調べた時、最も目を引いたのが京大でした。自由の学風によるユニークな思想、発想を持った学生達や、世界を変えうるような発明、発見が数々される研究力はとても魅力的に見えました。当時の僕は生物の勉強がとくに好きだったので学部を農学部にいったん絞り、その中でも応用生命科学科の細胞生化学に興味を持ちました。ヒトの細胞の中で働くタンパク質やコラーゲンの生体物質の研究を通して、がん等の疾患や生活習慣病の克服を目指す研究はとても興味深く、応用生命科学科を志望しました。
●受験勉強の仕方
僕は集中力があまりないほうだったので勉強時間を確保するよりも質を上げることに注力していました。一つ目の質を上げる策は、短いスパンの計画を練らず、長期目標をアバウトに作り、自由な勉強をすることです。僕は一日ごとの計画を作ってしまうと、満了すれば気が抜けるし、間に合わなさそうだったらやる気を失ってしまうという人間だったので、長いスパンの計画によって余裕をもって調子がいい日は長く勉強し、調子が悪い日は短時間勉強することができ、ストレスを貯めず集中して勉強を続けられました。もう一つも似たような策ですが、その時やりたい勉強をやり続けることです。興が乗らず、楽しくできない勉強は集中がたびたび切れて効率が悪いので、自習室では好きな勉強をずっとやり続け、嫌いな勉強は塾の先生や友達とやることでとにかく長時間勉強し続けました。僕の勉強方法は全く王道と外れているものですが、もしこれを読んでいる皆さんが勉強方法に迷っているのならば僕の方法を試してみると案外あっているかもしれません。
●受験生に向けて一言
高校が別に進学校でなくとも結局本人の努力次第で受験はどうにかなります。受験レベルで勉強するのは普通人生で一度だけなので楽しみながら勉強を進めて、京大で楽しいキャンパスライフを過ごしましょう。
農学部:地域環境工学科
ペンネーム: ゆでたまご
●京大を目指したきっかけ
高校に入った頃は、漠然と地元の大学に進むことを考えていました。また、農業と機械工学に興味があり、農学部と工学部のどちらに進むか悩んでいました。しかし、高校の進路講演会で京都大学農学部に進学した先輩のお話を聞く機会があり、京大に興味を持ちました。そこで京大農学部の学科を調べ、地域環境工学科で農業と工学の両方を学ぶことができると知り、京大を第一志望に決めました。平安時代の文化などが好きで、京都での生活に憧れがあったことも京大を目指したきっかけの一つです。
●受験勉強の仕方
農学部は比較的共通テストの割合が高いです。また私は京大の二次試験の形式がかなり苦手でした。自信をもって京大に出願するためには共テで良い点数を取ることが必要だと考え、共テの勉強にもある程度時間をかけました。特に配点の高い社会や国語の暗記事項は、4月から少しずつ覚えるようにしていました。
受験勉強で最も重要なのは基礎固めだと思います。私は浪人して合格したのですが、現役時はどの科目も基礎を理解できていない状態で過去問演習を始めたことが不合格の原因だったと思います。浪人してからは、秋までは予備校のテキストの予習と復習を中心に勉強しました。少しでも分からないことがあったら基礎に戻ったり質問したりすることで、疑問点を残さないようにしていました。周囲の受験生は過去問を進めている人も多く、差が広がっているだろうと不安になりましたが、基礎を固めてから12月以降に過去問を始めると、現役時とは違い実力がついていることを実感できました。問題演習を進めるにつれて少しずつ不安も消え、自信を持てるようになりました。
また、特に苦手科目では自分に合った先生や参考書を探すことが重要だと思います。私は物理と地理が苦手でしたが、予備校の先生の授業との相性がよく、最終的には安定して点数が取れる科目になりました。
●受験生に向けて一言
受験勉強をするうえで、体調管理は特に重要だと思います。私は秋に体調を崩し、思うように勉強できないことが増えました。しっかりと睡眠や休憩を取ることは勉強の効率を上げるためにも必要です。不安を感じることもあると思いますが、あまり気負いすぎず、適度に気分転換をしつつ頑張ってください。応援しています。
農学部:森林科学科
ペンネーム:明日の神話
●京大を目指したきっかけ
自分の高校では京大の合格者は毎年それなりにおり、京都大学というのが目指すべきゴールのようになんとなく掲げられていました。しかし個人的には、兄が京大生であったというのが京大を志望する大きなきっかけだったと感じます。兄がいなくても京大を目指していたのだろうとは思いますが、同じ家で暮らす兄が京大で生活していることが京大というものを強く意識する要因になっていたことは確かです。また京大の森林科学科が自分の学びたいことと非常に親和性が良かったことも大きな理由です。
●受験勉強の仕方
自分は現役で、8月上旬まで学園祭と部活の大会で大わらわだったので勉強をあまりしていませんでしたが、基礎はそれなりに習得していたので、夏の模試は悪くありませんでした。しかし、秋にかけて普通なら赤本で本番の形式に親しむなど実践的な勉強をすると思いますが、自分は基礎を補強するため問題集ばかり解いていました。その結果入試問題の形式に適応できず、秋の模試の偏差値が15ほど下がり、得意だと思ってあまり勉強していなかった英語がてきめんに悪化しました。しかしその後、兄や親に助けてもらいながら、これからどう勉強すべきかを考えたことが合格した大きな要因になったと今思います。模試が返却されたのが12月中旬、そこから必死で赤本の問題を解き続けました。過去問は教授が1年間かけて考えたものなので、問題集とは全くモノが違いました。解き直しを何度もしました。大切にしたのは、「わかっているけど解けていない問題」をなくすことです。ケアレスミスも誰も解けなかった問題も同様に点が減ります。解ける問題を確実に取ろうと考えました。共通テストに関しては、基礎はやはりそれなりにできていたので、2週間ほど市販の問題集で学びました。共テ後はやらずにとっておいた直近数年分の問題を、時間をはかりながら通しで行うことで、問題を選ぶ力を身に着けました。この期間は友人関係にもとても悩みましたが、ここで勉強をして、自分が受かることは、結局自分のやってきたことを肯定し、つまり友人を肯定することにもつながると思い、あまり話をすることはなかったです。みんな落ちるより、少しでも多くの人が受かる方が良いと今でも思います。
●受験生に向けて一言
できることのなかで最善を尽くすことは、陳腐な物言いですが大事です。「入試まであと1か月なら基礎を解きなおすのは不可能に近いかもしれないけれど、苦手なあの単元だけなら復習できる。けれど、今は過去問をやって入試の形式に慣れ、得点を底上げするのが一番良い。」このように、できることを考え、そしてすべきことを実行できれば、物凄く力になります。できる勉強、できる問題、できることを出し尽くせば、良い結果になると私は信じています。
農学部:食品生物科学科
ペンネーム:ヨーグルト
●京大を目指したきっかけ
私が京都大学を目指した一番初めのきっかけは、高校の先生に勧められたことでした。そこで、実際に志望校として京都大学を書いてみたら思ったよりも良い判定をもらうことができて嬉しくて、京都大学を目指したいなと思うようになりました。食品生物科学科を目指したのは、食べることが好きで食に関わる仕事に就きたいと思っていたからです。
そして、高校2年生の夏休みにオープンキャンパスに行ってみて、実際の実験設備を見せてもらったことで、京都大学で学びたいなと思う気持ちが強まりました。そこから京都大学を目指してひたすら勉強していくうちにますます、京都大学に行きたいという気持ちが高まっていたように思います。
●受験勉強の仕方
正直なところ私が京都大学に合格できたのは中学校、高校1、2年生の積み重ねであったと思います。中学生では基礎をしっかり固めていたため、高校の勉強でも苦労することなくついていくことができました。そして、高校1、2年生からは模試の結果を意識して、自分の苦手な分野を見つけ、その分野を重点的に勉強していきました。高校2年生の秋からは、京都大学を意識して、数学は京都大学の数学3を使わない問題を解き、英語と国語は過去問に少し触れてみたりしました。物理と化学はまだ習っていない分野が多かったので、習った範囲の応用問題がのっている参考書を利用して勉強しました。
そして、高校3年生からは、実際に先生に添削してもらい、どうすれば自分の解答が良くなるのか聞きました。そして京大模試の結果を受け、どこが足りないのかを分析して、そこを重点的に勉強しました。私は物理と化学がとても苦手だったので、赤本を受験までに2周できるように解き進めていきました。加えて、農学部は共通テストの社会の配点がとても高いので、隙間時間があれば社会の勉強をして、間違えた問題をルーズリーフにまとめ、その復習をしました。
●受験生に向けて一言
頑張って勉強しても思ったような結果が出ないことや計画通りにはいかないこともあると思います。そんな時は自分を責めすぎないでください。勉強したことはどこかに身についています。そして、受験はやはりとても緊張しますし、強いストレスを感じると思います。それでも、それまで積み上げてきた努力はきっと力になっていると思います。悔いのないように本番に向けて用意をし、合格をつかみ取ってください!応援しています!
農学部:資源生物科学科
ペンネーム:クロアリ
●京大を目指したきっかけ
関東出身ではあるものの、なぜか阪神ファンということもあって関西への憧れがあったことで関西の大学への進学を高2の2月ごろから本格的に考え始め、3月に京阪神の大学を友人と見に行きました。その際に感じた京大の神々しい感じ(?)や、親しい友人が京大を目指していることに影響を受けて京大を目指すようになりました。また、自分の興味のある分野の研究所は、日本では京大にあるものが一番古いことなどにも魅力を感じました。
●受験勉強の仕方
勉強を始めたのは高2の2月で、自分自身中高一貫校出身ということもあり、英語の勉強から逃げ続けていたので、まず英語の勉強からスタートしました。まあ結局現役では落ちて浪人していて、現役時代の話は参考にならないと思うのでここらで割愛させていただきます。
現役時代僕は数十点差で落ちました。浪人期はまずその開示をみて敗因と来年どのような点を取って受かるかの目標を決めました。敗因はざっくりいうと、英語の勉強を始めるのがあまりにも遅かったことで、全体として数学の点次第の成績になっており、その数学がかなり難化したことでした。なのでまず、比較的安定すると言われる英語や理科を重点的に勉強しました。
英語は予備校で薦められた、授業でやった文章の音読を毎晩しました。これによって頭の中で構文がより早く処理できるようになり、京大の英語は一文一文が重いことが多いですが、それを早く正確に読めるようになりました。これはリスニングの学力の向上にも役に立ちました。英単語は予備校と自宅の往復が約2時間あったので、その時間に覚えていました。
次に理科についてですが、僕は物理と化学を選択していました(高校になぜか生物選択がなかった)。物理は予備校の授業でとった板書を自分で再現できるようにし、化学はとりあえず、無機化学などパッと見て答えや解法が思いつくものを確実に取り切れるように勉強しました。
数学は合格者が取り切るであろう問題(2025年でいうと大問1や3など)は最低でも取り切れるようにしました。とにかくまずは基礎内容を確実に理解し、問題を見て瞬発的に使えるようにするのが大事だと思います。
結果としては、元々得意な理科で稼いで、英数は合格者平均くらい?をとって最初に決めた点数とほぼ一致する形で点を取れたのでよかったです。
●受験生に向けて一言
支えてくれる両親や先生、助けてくれる友人への感謝を忘れずに、受験期を全力で駆け抜けてください。
特色入試合格者体験記
文学部
ペンネーム:モユ
●京大を目指したきっかけ
中学生の頃からうっすらと京大への憧れを持っていました。京大を志望校に決めたのは高一の冬で、関東や実家や中高一貫校といった限られた場所で育まれてきた自分の価値観の狭さに疑問を抱いたのがきっかけでした。もっと広い視野を持つために、関東を出て一人暮らしをしてみたいと思うようになりました。当時好んで読んでいた本の著者の多くが京大文学部出身だったこともあり、自然と京大文学部を目指していました。
●受験勉強の仕方
高二の3月に特色入試の存在を知り受験を決めました。特色入試で合格することは、はなから期待しておらず「受けなかったら絶対後悔するだろうから」と考えて決断しました。とはいえ特色入試の準備は時間的にも精神的にも苦しいときもありました。「特色を受けたことを後悔しないように、特色の準備も一般受験の勉強もどっちも頑張る」と決めて踏ん張りました。
学びの設計書には夏頃から取り組み、担任の先生と何度も話し合いを重ねました。私には目立った受賞歴はなかったので、自分の学びたいこととそれに関するこれまでの経験を書きました。出願のために用意したものではありますが、これまでの学びの集大成、そして未来設計図として書いておいて良かったなと思っています。
HPに公開されていた2年分の過去問だけを解いて小論文試験当日を迎えました。午前の論述試験では少し手応えがあったものの、午後の要約問題で英文が理解できずに落胆。「こうなったら私の好きなことを全部書いて読んでもらおう」と決意し、普段よく考えていたことや自分の文学観を小論文に盛り込み提出しました。
学びの設計書についても、小論文についても、普段から興味のあることについて思索を深めることや、そうした考えを自分なりに言語化してきたことが役に立ちました。
●受験生に向けて一言
特色入試は「ダメで元々」という気持ちで受けていたので、合格した時には本当に驚きましたし、特色の受験をサポートしてくださった高校の先生方には頭が上がりません。
学びの設計書にも小論文にも正解がない分、不安になることもあるかもしれません。でも、その分野を学びたいと思うに至った自分の経験・思索があるはずです。そんな自分のこれまでの経験を何よりも信じて頑張ってほしいです!
法学部
ペンネーム:Sägemehlchen
●京大を目指したきっかけ
私が京都大学を志望するようになったのは高校二年生の頃でした。当時の志望理由は至極あいまいなもので、恐らく確か京大の関係者の各界でのご活躍や自由の校風という評判に惹かれて、という形でした。しかし、その後現在進行中の国際関係や人権問題に関心を持つにつれ、素晴らしい先生方や優秀な仲間、豊富な蔵書を始め、極めて良質な教育環境を有する京都大学法学部で学びを深め、どうにか社会に貢献しうる人材となることを希望するに至りました。
私自身は大した才能や業績があったわけではなく、当初は特色入試の利用をあまり考えていませんでした。どちらかと言えば親の勧めで受験を決めました(感謝しています)。
●受験勉強の仕方
特色入試対策を始めたのは高3の夏頃と学びの設計書の作成すらギリギリの時期でした。頭を捻って何とかひり出したつたない草稿をお忙しい中担任の先生に何度か添削いただき、確か二週間ほどで作成しました。いろいろあった末に二次試験、つまり小論文による論述試験の対策に進んだのですが、実は一次試験(書類審査)の合格通知から12月の二次試験本番までは二週間ほどしかなく、一般入試の対策もある中でかなりタイトなスケジュールになっていました。法学部の特色入試は私の年度が最初であったため、サンプル問題に加えて前身たる後期入試の過去問を用いて練習しました。学校の先生にも見て頂いたほか、専門の対策塾の教材も利用して猛勉強しました。正直言って共通テスト直前よりも勉強していたと思います。その中で感じたのは、日頃から社会の課題や国際的な問題について考え、意見を体系化しておくことの重要性です。立場を定め、大体の論の枠組みさえ作れてしまえば後は本当に一瞬で書けます。さらに、要約問題の練習に関しては小論文に留まらず他教科の読解や記述に際しても決定的に重要となるので、まだ特色入試を受験するか決めていなくても是非日頃から練習されることをお薦めします。
そうして対策を進めている内に二次選抜当日を迎えました。演習を重ねていたおかげか緊張はあったものの比較的落ち着いて試験に臨めました。問題は旧後期入試と比べればかなり易しかったと思います。…がしかし、安心して時間配分をなおざりにした結果、終盤で時間が尽きかけました。何とか根性で最低文字数に到達しました。実際はそれなりに時間に余裕はあるものの、時間配分にはくれぐれも気をつけてください。
その後なんとか二次選抜を通過させていただきました。通知が届くのは共通テストの1週間ほど前でしたので、それまで自信の有無にかかわらず必死で対策しました。次の3次選抜合格のボーダーラインは約8割とされており、このため余裕を持って共通テストを受験できたことは良かったと感じています。
●受験生に向けて一言
蓋し特色入試は、こと法学部において、一部の途方もない才能のある人にしか受けられない入試方式では決してなく、特色ある個性や活動、そしてここ京都大学での学修にかける情熱のある人にひろく開かれた制度だと思います。皆さんの持てるあふれる意欲や個性を大学に見せつけるためにも、また単に受験のチャンスを増やすためにも、ぜひ一度挑んでみてはいかがでしょうか。
医学部:人間健康科学科
ペンネーム:あいまい
●京大を目指したきっかけ
高校2年生の秋に体調を崩したことをきっかけに、医療や「人に寄り添うケア」に関心を持つようになりました。さまざまな大学を検討するなかで、オープンキャンパスで感じた京都大学の雰囲気や理念に惹かれ、「ここで学びたい」と強く思いました。高3の6月には特色入試での受験を決意し、一般入試は一切考えていませんでした。無謀な決断だったと思う一方で、「この道しかない」という覚悟が自分を支えてくれました。
●受験勉強の仕方
特色入試では、書類・論文・面接・共通テストのすべてが評価対象となります。
まず、学びの設計書は最重要だと考えて、就職活動のエントリーシートを参考に構成を練りました。自分の体験と将来像が自然につながるように意識し、「今の私にしか書けないこと」を素直に綴りました。何度も先生に添削していただき、提出直前まで書き直し続けたのを覚えています。
論文試験は3時間で課題文を読み、回答を作成するというもので、過去問は2年分しか公開されていませんでした。そこで、国語科の先生に紹介してもらった医学書院の「ケアをひらく」シリーズを活用しました。各本の内容を要約し、自分なりの考察を2000字程度でまとめる練習を繰り返すことで、書く力・考える力を養いました。添削指導は複数の先生にお願いし、同じテーマでも毎回新しい切り口を探すように意識しました。
英語対策では、医療系英語長文を中心に、語彙と読解スピードを高めました。普段の長文読解では「この内容を自分の目指す医療職にどうつなげるか?」を常に考えながら読むようにしていました。 面接対策は、実践的なトレーニングを重視しました。マナビジョンの体験レポートを読み込んで傾向を掴んだうえで、生成AIに症例を出してもらい、即座にどう対応するかを考える訓練を重ねました。また、試験1週間前の模擬面接では「もっと個性を出していい」とアドバイスを受け、自分の言葉で、自分の考えを伝えることを大切にするようになりました。
●受験生に向けて一言
特色入試は、自分の経験や想いを評価してくれる貴重なチャンスです。うまくいかない日があっても、自分を信じて、等身大の言葉で思いを伝えることを忘れないでください。そして、どんなに忙しくても、「ちゃんと寝て、ちゃんと食べること」。健康は最大の武器です。応援しています!
工学部:情報学科
ペンネーム:うまい棒(ウマイ味)
●京大を目指したきっかけ
高校入学前から京大には漠然とした憧れがありましたが、はっきりと意識するようになったのは高校から通い始めた塾で京大クラスに選抜された時でした。高1のうちは何となくで工学部を志望していましたが、高2で取り組んだ探究活動で情報の勉強をするうちに情報学科に行きたいと思うようになりました。先生と先輩から探究活動で特色入試が受験できると教えていただいて、特色入試を受けようと思いました。
●受験勉強の仕方
特色入試の対策は、一般入試の勉強と並行して秋から始めました。探究の授業でグループで書いた論文を何度も読み直して修正したり加筆したりしました。英語は全く話せませ んでしたが、英語でのポスター発表会に参加して、研究内容を英語で説明できるようにしました(ほとんど丸暗記でしたが笑)。直前には学校の先生に面接の指導をしていただいて、英語での自己紹介や数学の口頭試問の練習をしました。第二次選考の合格が分かってからは共テの対策に命を懸けました。数学IAが本当に苦手だったので共テ直前はそればっかりやっていました。
●受験生に向けて一言
特色入試は自分には関係ないと思っている人が多いと思いますが、自分のやってきた活動を振り返りながら、一度志望学科の募集要項を読んでみるといいと思います。情報学科を受験する人は口頭試問でめちゃくちゃ圧をかけられますが、負けずにしゃべり続けてく ださい!
工学部:理工化学科
ペンネーム:さらり
●京大を目指したきっかけ
目標にするのなら高いところをという考えから高 1 のころから漠然と「京大に行けたらすごいなー」と考えていました。成績も良い方だったので高1の冬頃から学校で受け始めた模試の志望校にも京大と書いていました。当時はすごく興味のある分野があるわけでもなく理系だということしか確実ではなかったので理学部と書いていた記憶があります。本格的に京大工学部を目指し始めたのは高2の秋ごろでした。私は特色入試で合格したのですが、当初は推薦を受験するつもりは全くありませんでした。ですが、学校の成績が良く部活動も頑張っていたので、両親や担任の先生から勧められて受験を検討し始めました。
「推薦のための準備に時間がとられてしまい一般の勉強ができなくなるのではないか」、「『絶対に京大がいい』というような強い思いや『顕著な実績』と言えるようなものはないのに大丈夫だろうか」という不安はありましたが、面接がないということもあり、チャンスを増やすための手だと考えて出願することにしました。推薦書類を書くにあたり大学 の学部や学科の特色を調べ、自分のやりたいことを見つめることで京大工学部理工科学科への進学希望が強まりました。
●受験勉強の仕方
私が受験した特色入試は、「学びの設計書」、「顕著な実績の概要」という受験生が書いた書類と、学校に書いていただいた書類、共通テストの成績による評価でした。学びの設計書では漠然とした内容にならないよう、できるだけ具体的に書くことを意識しました。顕著な実績の概要には、課題研究を行う高校の授業で行っていた研究活動や参加した研究発表会について書きました。その際、どんなことをしたかという事実だけではなく失敗や経験を通して何を得たかについても書くようにしました。共通テストは早い時期から過去問に取り組み問題形式に慣れることを大切にしました。特色入試は合格したらラッキー、あくまでも一般入試が本命という考えを持っておき、書類を提出してからは推薦のことをできるだけ考えず一般入試に向けて全力で頑張るようにしました。
●受験生に向けて一言
最初のきっかけは些細なことでも、私のように目指し始めてから「京大に行きたい」という気持ちが強くなることもあると思います。だからまずは行動を起こしてみてくださ い。大学について調べてみる、過去問を解いてみるなど少しの行動で「行きたい!」と思える理由が見つかるかもしれません。これからたくさん勉強する中で「行きたいから頑張ろう」と思えることは強みになります。皆さんのやりたいことが実現できるよう健闘を祈っています!